![]()
・・・「うっかり」は出来ません。
魚と関わることによってうける被害は毒によるものと、傷によるものがあります。
毒魚は『刺毒魚』、『中毒魚』、『粘液毒魚』にわけられます。
『中毒魚』でまず有名なのはフグ類で、その他にはシガテラ毒魚(バラフエダイやドクウツボが有名)、ナガヅカやタウエガジの卵による中毒も報告されています。皮膚の粘液毒魚ではヌノサラシやハコフグの仲間が有名です(人体に直接害を及ぼすことはまずありません)。
このページでは主に有名な『刺毒魚』について述べていきたいと思います。
![]()
※刺毒魚 
魚の刺毒はタンパク質からできています。ただ非常に不安定で、すぐに毒性が消えてしまううえに魚1尾あたりの毒もごく微量であるために、研究は非常に難しく詳しいことは何もわかっていません。タンパク質でできた毒が「痛み」をもたらし、さらに「致死性」と「溶血性」をもたらすと言われています。
ヒトが刺毒で死ぬこともあるのは、その毒性によるもの、異種タンパク質によるアレルギー性ショック、痛みによるショックなどが複雑にからみあっていることしか解明されていません。
![]()
|
鱗がほとんどない |
背鰭前方の棘は長い |
||||
|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
ハオコゼ |
大きくても10cm程度の小魚だが、背ビレ、尻ビレ、腹ビレの棘に毒があり、刺されると非常に痛い。ハリを外す時はラジオペンチなどを使って慎重に。
![]()
| 両眼の間は凹む |
背鰭棘は長い |
||||
|---|---|---|---|---|---|
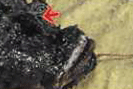 |
 |
 |
 |
 |
オニオコゼ |
オニオコゼは瀬戸内海などの内海の砂泥底に多い。背ビレで刺されると猛烈に痛み、瀬戸内の漁師は『満潮に刺されると潮が引くまで痛む』と言うらしいですが、実際の回復には数日から数週間かかり、死亡例も報告されています。どんな料理にも向く高級食材でもあります。
![]()
|
下顎腹面に斑紋が・・・ |
背鰭、臀鰭、尾鰭の暗色斑は・・・ |
||||
|---|---|---|---|---|---|
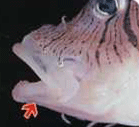 |
 |
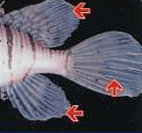 |
 |
 |
ミノカサゴ |
|
ない |
わずか | ||||
 |
 |
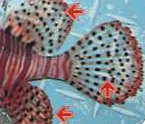 |
 |
 |
ハナミノカサゴ |
|
ある |
多数で明瞭 |
現在ののように水族館などで華麗な熱帯魚が気軽に見れなかった時代は、少年にとってミノカサゴ類は憧れの魚でした。フサカサゴ科魚類としては強力な毒を持っているので注意が必要です。
![]()
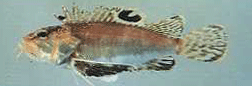 ハチ
ハチ
別名ヒレカサゴ。下顎に2対のひげがあり、胸鰭最下部に1本の長い遊離軟条がある。背鰭棘条部に1大黒斑がある。背鰭棘に毒がある。
![]()
 ゴンズイ
ゴンズイ
体に2本の黄色いストライプが走り、背鰭と胸鰭に毒棘を持ちます。この魚は毒棘を直立させて死ぬうえに毒は魚が死んでもその効力を失わないので釣り場などに放置するのは禁物です。
![]()
 アイゴ
アイゴ
黒褐色の地色に白い斑点が体表に散らばっているのが普通だが、環境の違いや興奮状態によって体色や斑紋を変化させる魚です。
和歌山や徳島などでは小さいものからバリコ、成魚はアイやアイゴ、さらに大きくなるとシブカミとかシブウチと呼び名をかえる人気魚です。
アイゴ特有の臭いがアンモニア臭と似ているため、イバリとかショウベンウオと呼ぶところもあります。格ヒレの棘には毒腺があり刺されると釣りどころではなくなるので注意が必要です。
![]()
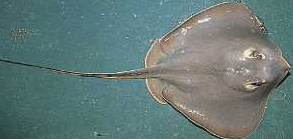 アカエイ
アカエイ
尾部背面に1〜3本の鋸歯を備えた大きな毒棘があり、刺されると危険。
この棘は後ろ向きについているが、尾を跳ね上げると棘が上から刺さるので、エイを釣っても踏んづけてハリを外さないこと。
![]()
毒棘に刺され「死ぬほど痛い」、「泣くほど痛い」とか言葉で済めばよいですが、ここで再確認。
刺毒・・・死ぬこともあるので注意が必要!!
まず刺されないようにすること、そして未解明の複雑なタンパク質であり、感受性はヒトによって異なるけれども、刺されて痛みが激しかったり、浮腫や発赤のある場合は大事をとって医者に行くこと!!
参考までに一般的な対処法。
傷口をきれいに洗い、できるだけ熱いお湯に1時間から1時間半、痛みがとれるまでを目安につける。これは痛みを取り除くのと血管の収縮を防ぎます。痛みに気をとられて火傷をしないように注意も必要。激痛が取れなければ病院で局部麻酔をしてもらい、棘が残っていないかレントゲン検査も忘れずにしてもらう。また破傷風などの注射もしてもらう。
おまけの話・・・
日本では奄美大島以南の浅いサンゴ礁や岩礁のくぼみにすむオニダルマオコゼ。魚というよりは石にしか見えない変な魚(下の写真)で、そのため釣り人よりダイバーや水遊びの人が踏んで事故になることが多いです。このオニダルマオコゼの毒は、今のところ刺されて痛む毒としては最強のものであり死亡例もあります。毒性を魚1尾で殺せる体重20gのマウスの匹数であらわすと、ハナミノカサゴは650匹、オニオコゼは230匹なのに比べオニダルマオコゼは〜26000匹。計算上ではオニダルマオコゼ1尾で体重60kgの人を4人殺せます。背鰭の毒棘が13本あるので、3本ほどの毒が体内にはいると死ぬ可能性があります。オニダルマオコゼの毒はあまりに強力なのでよく研究されており、毒も精製され抗血清も開発され、オーストラリアでは「ストーンフィッシュ・アンチヴェノム」という市販薬にもなっています。この抗血清は日本のオニオコゼやミノカサゴにもある程度効くことが確かめられていますが、刺されてオーストラリアに行くわけにもいきません。日本には刺毒魚に効く薬はありません。
 |
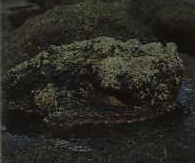 |
 |
![]()