メバル・ガシラ(カサゴ)明石沖・神戸沖
冬釣りの定番!
| 明石海峡周辺:アジロ紹介 | 鹿の瀬周辺:アジロ紹介 |
|---|---|
 |
 |
| サビキorエサ釣り | ルアー | タックル紹介 |
|---|---|---|
 |
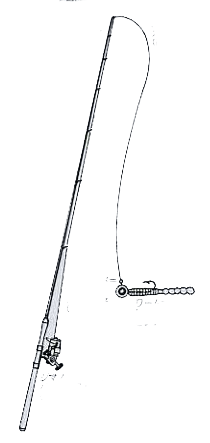 |
《サビキorエサ釣り》 船竿30〜50号 〜3.5m 緑色に着色したサバ皮 エサはシロウオ、冷凍のイカナゴ、海ゴカイなど 六角オモリ〜50号 《ルアー》 ルアーロッド 〜6.8ft 道糸:カーボン3LB ジグヘッド=がまかつ16分の1 ワーム=1.8in(約4cm)色・・・ピンクなど |
まずは明石海峡大橋沖のポイントについて。
明石海峡は潮流がかなり速いので、カサゴを釣ることができるのは潮止まり前後の短時間に限られます。それでも一艇あたりの釣果は中潮や大潮の日で50匹前後。潮流が穏やかな長潮や若潮の日には100匹以上釣れることもあります。明石大橋北側の橋端あたりの水深は40m前後。ポイント付近の海底には大小の捨て石が散在しています。
もう少し詳しく述べますと、明石海峡大橋の橋脚周辺は、基礎部分から50〜70m沖まで大小の捨て石がビッシリと入っており、その沖は崩れた捨て石が散在する砂泥地で、捨て石上の水深は40〜15mです。
おもりで底が取れないほど流れが速くなった時は淡路島北東岸沿いの水深5〜6mの浅場にある沈礁周辺に移動すると良いでしょう。
明石大橋沖のカサゴは3月下旬頃まで安定した釣果が望めます。一帯の(明石大橋)潮流は満ち潮が東から西方向へ、引き潮はその反対方向に動きます。上でも述べましたが、橋周辺で釣りになるのは大潮の日で潮止まりの30分前後、長潮の日で1時間半〜2時間です。
釣り方は流し釣りで冷凍のイカナゴを仕掛けにセットして釣ることがほとんどです。仕掛けが着底したら、竿先を上下させて誘いをかけます。仕掛けが海底から50cm以上離れると極端にアタリが少なくなるので注意が必要です。イメージとしてはオモリで海底を軽くたたく感じで探るのが良いです。アタリがきて針掛かりしたら捨て石の間に入られないように素早く底を切り、底から離した後は一定の速度で巻き上げます。水深が深いところで狙うときは伸びが少なくてアタリが明確に出るPEラインの方が有利だと思います。このポイントでは根掛かりが非常に激しいので仕掛けは余分に用意しておくほうが良いです。
次は神戸市のポートアイランドや和田岬などの沖のポイントに(六甲アイランド沖でも釣れます)ついて。神戸沖のメバルは5月も釣れ続きます。
ポートアイランド沖のポイントは人工島の岸壁際に入っている捨て石の際になります。このポイントも根掛かりは多いです。干潮時の水深は岸壁の10m沖で約7m、15m沖で12m前後です。潮流は満ち潮が東から西方向へ、引き潮はその反対方向に流れます。この辺りではゴカイをエサに釣っている船が多いです。流し釣りで、基本は海底付近を探るとよいと思います。底層でアタリが散発的になってきたら仕掛けを中層まで上げるとよいでしょう。メバルがエサに食いつくと、最初に小さなアタリがきます。このときはエサをくわえているだけなので合わせを入れてもエサの端を食いちぎられるだけで針掛かりしないことが多いです。小さなアタリの後に明確なアタリが出るので、この時点でゆっくりと合わせるとよいでしょう。1匹ずつ釣り上げてもよいですが、合わせたあとに仕掛けをそのままにしておくと、メバルが追い食いして2、3連で釣れることもあります。
ポートアイランド沖や六甲アイランド沖、または和田岬東沖ではソフトルアーを使ったルアー釣りも盛んです。ルアーで底付近を探るときは、オモリが着底したあと、竿先を上下にチョンチョンと小さく動かしながら誘います。メバルのライズ(表層でエサを捕食しようとした魚が海面で反転すること)があった時などは表層を探るとよいです。時期的に水温がかなり低くなっている冬の時期ですが、水温が10℃ほどあるような時はかなり釣果が期待できます。一般的にルアーで狙うときはまず表層を攻め、アタリがなければ徐々に深い層を探ります。ルアーの引き方は、ゆっくり巻き上げながら時々細かく竿先を動かして誘います。食いの悪いときは無理な合わせをせずに、アタリがきた後は向こう合わせで針掛かりさせたらよいです。カサゴを狙うのであれば、最初から底付近を底オモリ式の仕掛けで狙うとよいかと思います。着底後、オモリで底をたたくような感じで竿先を小さく上下に動かしながら手前に仕掛けを寄せます。カサゴの場合はアタリがあったら敷石やテトラなどに潜られないように素早く合わせた方がよいです。
次は少し遠いポイント、家島諸島東部の鞍掛島から約5.5キロ南沖の沈船ポイントについて。
根掛かりが多くて釣りにくいポイントですが良型が釣れるのが魅力な場所で、例年だと5月ころまで安定して釣れ続きます。このあたりではシロウオをエサにした仕掛けや、活性が高いときはサビキでもよく釣れます。場所が遠いせいか貸し切り状態になることも多いです。沈船周辺の水深は約32mで、沈船の長さは100m前後あります。流し釣りで沈船の影が消えたあたりで潮上に戻る感じで釣ります。メバルの活性が高いときはアタリがきてもすぐに仕掛けを上げずにしばらく待って追い食いを狙います。このポイントは底スレスレで釣れることが多いです。このポイントではメバルの他にもソイやハネ、スズキの実績も高いです。
沈船周辺の海底は平坦な砂泥地で水深は32m前後で、沈船の一番高い部分の水深は約26mです。当たり前ですが沈船の上では根掛かりが多いです。一帯の潮流は満ち潮が東から西方向へ、引き潮はその逆方向へ流れます。メバルは満ち潮、引き潮ともによく釣れますが、一番実績が高いのは午前中の満ち潮のようです。中潮と大潮の日がかなり狙い目です。メバルは沈船の潮上側でよく釣れることが多く、満ち潮時は沈船の東側、引き潮は西側に起点を取って流します。基本はサビキとエサを併用した胴付き仕掛けです。エダスは0.8〜1号。仕掛けが着底したら海底から1.2m浮かせてゆっくり上下に誘います。1匹掛かったら根掛かりしないように仕掛けを少し上げて追い食いさせると効率よく釣れます。
とりあえず大きく分けて3箇所について述べましたが、ポイントとしては水深数メートルのところから60〜70メートルの深いところまで数多くあります。実際の釣りでは1箇所にはとどまらず、潮の流れが悪くなると潮のよいポイントにどんどん移動しています。海底の状態も岩場から粘土まで様々で、潮回りによって狙うパターンが決まってきます。
他地域ではマキエをしながら釣るところも多いようですが、明石海峡付近ではマキエが出来ないので(潮が速いから)食わせるのにはテクニックが必要になってきます。ただ、この辺りのメバルは潮の速いところに生息しているので肩の部分が盛り上がって肉厚もあり、身がよく締まっています。
広範囲に場所を移動したりするので、基本的に何かと間違いの少ないPEラインを使用しています。エサもシーズンなどによって変わり、シラサエビやイカナゴなどを使用します。メバルは磯、ブロック、海底のかけ上がりなどのデコボコしたところや、海草や海藻などが群生している障害物をすみかにしています。