・・・主に釣りの学校で登場した魚たちを紹介します。
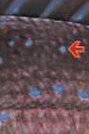

キス(鱚)
黒い
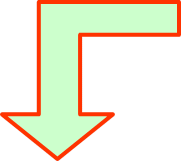
ある
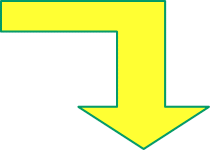
ない
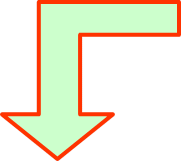
「きす」といえばシロギスじゃないか!それほど沿岸の砂の所には必ずいる「日本の魚」。しかし日本産キス科は1属4種、世界で見れば3属30種いることも一応頭に入れておきましょう。
キス科の魚は『熱帯魚』であり、インド洋から西太平洋の熱帯を中心に温帯まで広がっておりクロダイ属の分布とよく似ています。シロギスはキス科のなかで温帯によく適応した「北限の種」なのです。琉球列島にホシギスやモトギスがいてよく珍しいと思われていますが、この2種は温帯には広く分布し、沖縄が北限なのです。
珍しくもなく釣りにくいわけでもなく、それでも人気が高い「変な」魚がシロギスです。姿が美しく可憐なくせに大きな魚信が釣り人の心臓を直撃するのでしょうか?「小さな大物」万歳!!
シロギスより大きくなり40cmを優に超えるのがアオギス。東京湾などでは脚立を海中に立てる(アオギスは船縁をたたく波の音さえ嫌うから)独特の『脚立釣り』が発達していましたが、いつのまにやら姿が見られなくなってしまいました。現在では九州と山口県以外での報告は長い間途絶えてしまっています。ただ「キス」=「シロギス」しかいないと思い込み見逃されているケースもあるかもしれません。しっかりと見て記録し、アオギスを絶滅種にしないための地道な情報集積が不可欠だと言われています。
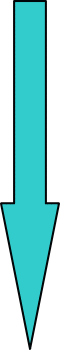
※青色斑が短い
線状ならヒレコダイ
(写真省略)
マダイ


黒く
ない
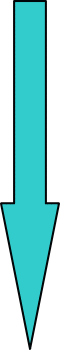

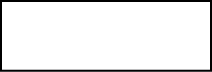
琉球列島に分布していなくて
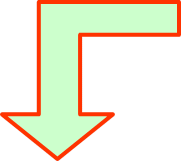
白色か無色
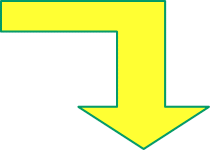

黄色


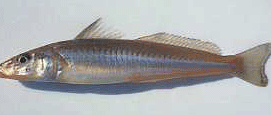

シロギス
アオギス
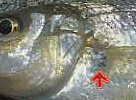
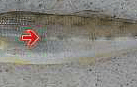

胸鰭基底に黒色斑がある
(※薄くても必ずある)
体に暗色斑が出る
(※出ないか薄い場合もある)
ホシギス


琉球列島に分布していて・・・
アオギスは水の澄んだ河口の干潟にしか住めないのです。川の水質が“まし”になってきている所では(西日本)アオギスが戻ってきているという『噂』もあるそうです。キスを釣ったら腹鰭を見る癖をつけなければいけないのかも・・・。
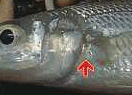
胸鰭基底に黒色斑がない


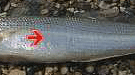
体に暗色斑が出ない

モトギス
アイナメ(鮎並)
関西では冬場から春(GW頃まで)にかけてが最盛期のアイナメ。釣りものの少ない時に釣り師のお相手をしてくれる貴重な魚!!冬のスターの座を「カレイ」と分ける魚です。
関東を除く広い地方で“アブラメ”と呼ばれており、また北海道ではアブラコと呼ばれています。地方によって異なりますが35cmをこえるあたりから『ポン』と愛称するようになります。『ポンが釣れた!』と釣り人は自慢しますが、さてさて語源は何なのでしょうか?関西では40cm級までは狙えます。50cm超の大アイナメを狙って北海道や東北まで遠征する釣り人もいるとか・・・
アイナメは「クセがあっておいしくない」という人も少なくありませんが、鮮度の問題ではないでしょうか?釣りたてで保存のよいものは刺身にしても煮つけにしてもおいしいです!!
体色は普通は茶褐色ですが、すむ場所や深さによってさまざまに異なります。いずれにしても濃淡の複雑なまだら模様なので、周辺の環境によく紛れ込んで身を隠しています。
ハリに掛かると首を振って“イヤイヤ”をするような独特な引き味がありますが、貪食なわりには警戒心が強くてエサとりがうまいです。
アイナメ科魚類は日本に2属7種、世界で3属9種。日本にそのほとんどが棲む北部北太平洋の魚です。ウサギアイナメ、スジアイナメ、エゾアイナメなどは本州の南部には分布していません。
アイナメにそっくりの魚でアイナメよりは味が落ちる(?)のがクジメ。アイナメほど大きくはなりません。北日本以外ではほかのアイナメ属が混じらないので見分け方は簡単です!!
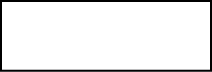
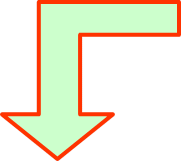
直線か浅く湾入
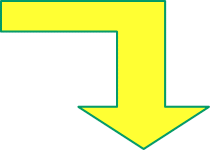
※側線は5本
※側線は1本
アイナメ(アイナメ科アイナメ属)
クジメ(アイナメ科アイナメ属)
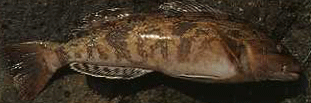







カサゴ(笠子)・・・(フサカサゴ科カサゴ属)
目の前のエサがあると見境なしに飛びついてくる卑しいせいか、釣りものが少なくなる冬場にしか見直されない魚がカサゴ。
大きな口をあけて簡単に釣れると嫌がる釣り人も多いです。
カサゴは関東では「かんこ」、関西では「ガシラ」または「アカメバル」の愛称で親しまれています。頭でっかちの魚だから、頭(かしら)がなまってガシラになったと言われています。煮つけにすれば後述するメバルより間違いなしに上ではないでしょうか?
体の地色はすむ場所や深さなどによってさまざまに変化します。深所に棲むものは赤い傾向にあるようです。
カサゴを思い込んでいて「うっかり別の種であることを見落としていた」から名づけられたのがウッカリカサゴです。ただ、これらの両種は混生もしており確かな見分け方は(遺伝子的にはカサゴとウッカリカサゴ、斑紋に違いがでるそうです・・・)まだ存在しないようです。関東では「かんこ」、関西では「沖ガシラ」と呼ばれる深場の大型カサゴです。
尾鰭後縁が丸くない⇒黄色波状線がない⇒体色は普通茶色っぽい⇒胸鰭中央の暗色斑が濃い⇒カサゴ
⇒体色が普通赤色っぽい⇒ 〃 薄い⇒ウッカリカサゴ
側線付近に白斑があり濃い縁取りがあればウッカリカサゴ、白斑がないか、あっても縁とりがなければカサゴ。
その①
その②

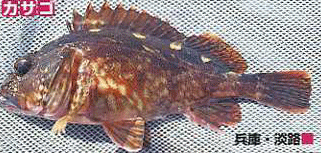




大男のひとりごと・・・私はうっかり者で結構です![]()
メバル(目張)・・・(フサカサゴ科メバル属)
少し潮の甘い内海や内湾に多いのがメバル。名の由来は、目を精いっぱい見開いたように見えるところから、目張(めばる)と呼ばれるようになりました。日本産メバル属には31種もいて、俗には「めばる」「そい」「めぬけ」と呼ばれる3群がいるとも言われますが、いずれの研究室もまだ混乱しているようです。「混乱を楽しむ魚」なのかもしれませんね?
ただ面白いのは変異がこれほど大きいのにメバルは『メバル』だと分かってしまうこと!
メバル属はあまりにも複雑すぎ、解明も出来ていないようなのでここでは簡単に紹介しておきます・・・




メバル
トゴットメバル
ウスメバル
クロソイ
メバルは体側の斑紋が薄く、乱れる傾向があります。あとの変異はそれぞれが楽しんでください・・・。冬場から早春に活発に釣れて、春告魚とも形容されます。瀬戸内東部では船釣りが盛んです。
メバルより少し深い沖の岩礁帯に多いので、「沖メバル」と呼ばれます。よく見ないと区別しにくいですが、トゴットメバルは背に黒い斑紋がはっきりしていて輪郭が丸みを帯びます。ウスメバルは背の斑紋が丸くなく形も不ぞろいです。
西日本で『ソイ』と呼ばれている魚はほとんどがこのクロソイです。もともと北の海に多い魚なので東北や北海道に行けばもっと仲間が増えるようです。大阪湾や瀬戸内海ではイカナゴのエサや生きエビがよく使われ、冬は乗合船での釣りが盛んです。


タイ(鯛)
日本人の大好きな魚は「たい」!普通にはいちばん有名、かついちばん好まれる魚であるのではないでしょうか?それ故に「○○鯛」などと語尾に「たい」のつく、いわゆる「あやかり鯛」も多いですが本物の「たい」はマダイやクロダイなどのタイ科の魚たちだけです。
“めで「たい」”とか“高い官位をさす「大位」”のことだ、などと色々な“いわれ得”をしていますが平安中期の法典「延喜式』に平魚(タヒ)とあり、実は“平たい魚”という意味でしかないのです。先程「あやかり鯛」が多いと書きましたが、「あやかり鯛」も平たい魚であるわけで、「あやかってなどいないぞ!」と怒られるかもしれませんね(?^.^?)
タイ科の魚たちの王様が『マダイ』です!太古から日本人の心を惹きつけてやまない魚のひとつではないでしょうか?
いかにも魚らしいスタイル、淡泊でいて深みのある味、釣り上げるときの引きの強さ、と釣魚として必要とされる価値をすべて兼ね備えた魚だと私は思うのですが・・・。
船釣りのマダイのシーズンは春の上りダイ、桜ダイに始まって、晩秋の落ちダイまでが一般的です。産卵期が3~6月頃で、この時期には深みから沿岸に近づき、産卵を控えたマダイは体色がとりわけ美しくなり(桜ダイ)味もよく値も高いです。
メーターを超すような超大物もいるようですが、そこまで大きくなるとおいしくはありません。
これだけの人気のある魚なのに地方名は少なくて、関西では当歳から2歳くらいの幼魚を『チャリコ』と呼びます。化学的な話をひとつ入れると、マダイがおいしいのは高度不飽和脂肪酸が少ないので変質しにくいためです。料理はここで述べるまでもなく何でもOKですが、タイのデリケートな味を生かすには、味を薄めにして火を通しすぎないことです。“うまみ”は皮と肉の間に隠されているので、刺身でなければ皮をつけたままの料理が最高です。
「たい」はマダイであると知っていても、『「たいの仲間」は?』と聞かれると困る人が多いのではないでしょうか?
日本産タイ科魚類は7属13種と少ないです。タイ科は「赤い鯛」のマダイ亜科とキダイ亜科、「黒い鯛」のへダイ亜科に大きくわけられます。釣りで狙われるのはマダイ亜科4種のうち、マダイ・チダイ。キダイ亜科3種のうち、キダイ。ヘダイ亜科6種のうち、クロダイ・キチヌ・ヘダイです。
釣りの対象魚でマダイ以上に人気のあるのがクロダイです。クロダイはまぎれもなく「タイの仲間」です。
クロダイは古くから人気のあった魚だけに地方名が非常に多く、関西では『チヌ』(成長段階に応じて、ババタレ・フタツ、またはマツ・チヌ、などなど・・・)と呼ばれます。ババタレは釣り上げたとたん脱糞する幼魚の習性から名付けられました。
関東では1年魚をチンチン、2~3年魚をカイズ(ケイズはカイズがなまったもの)と呼びます。チンチンのイントネーションは?と思ってしまう大男でした(#^.^#)
まったくややこしい地方名や幼魚名。まあ見方を変えればそれだけなじみ深い証拠なのでしょうが・・・
賢く、釣りにくく、沿岸のどこにでも潜んでおり、磯釣り・波止・かかり・投げ、などなど釣りのジャンルを選ばないためにクロダイに釣り人の人気が集まります。好奇心旺盛だが神経質な魚で地方地方で工夫を凝らした繊細な釣り方が発達しています。悪食であることも有名で人間の食べるものならほとんどエサになります。スイカやコーンでも釣れます。日本記録は69.5cmだとか・・・。60cmを超える大型を釣る確率は宝くじより低いらしい・・・。これほど人気のある魚なのに、「釣るのは好きだが食べるのは・・・」という釣り人も多いのがなんとも不思議。肉質がやわらかくて、少し水っぽいせいでしょうか??
(個人的な意見ではありますが、私は自分で釣った魚を食べないのは釣りではない!と思っています。だからバス釣りは大嫌い・・・。キャッチアンドリリースなんて言葉も大嫌い!!)
私個人的にはあまりになじみのありすぎるクロダイより、ハリに掛かると「まっすぐ」走り、あきらめると「スパッ」と浮いてくる潔さ、そして魚体の艶やかさ、「桜」に通じる「日本人の心」のある(?)マダイの方が興味が惹かれますが、皆さんはどうでしょうか?
※体に3黄色斑がある

キダイ

キダイ・・・西日本の呼び名「れんこだい」で有名ですが釣りではあまり狙いません。背部に大きな黄色斑があり、独特の顔つきなのですぐに区別できます。福井県の名産「小鯛の笹漬け」に使われます。あまり大きくならず40cmを超えません。水深が100m以上の深い海でアマダイなどを狙っているときに派手なアタリで食ってきます。

チダイ
チダイ・・・マダイとチダイくらい見分けられると簡単に考えている人も多いですが、非常によく似ているものもいるので注意。一番の見極めは図で説明した尾鰭後縁です。「たい」を釣ったらここを見る癖をつけましょう。なんでも「鯛のうち」なんてちょっと寂しすぎます・・・
漢字で書けば「血鯛」です。鰭蓋後縁が血のように赤いからという語源説もあります。「ちだい」は西日本の呼び名で東日本では「はなだい」と呼び専門で狙います。西日本ではあまり狙わず、マダイに混じる「鯛のうち」ではないでしょうか?あまり大きくならず40cmで最大クラスです。産卵期が秋なので関東では春よりも秋のシーズンに釣りが盛んです。
身が少し柔らかく味はマダイに落ちると言われますが、うまいです!
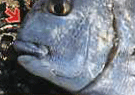

へダイ

・喉はまるい
・臀鰭軟条数は11
ヘダイ・・・内湾に多く、クロダイを狙っているときにときおり外道として掛かるのがヘダイです。変なクロダイだなぁ・・・間違う人もいますが、体に十数本の薄い縦線がでるのでこれをチェックしましょう。確かに似ていますがクロダイほど口がとがっておらず、全体も丸い感じ。釣り上げた瞬間のヘダイは、クロダイより色が白く、鱗も小さいために白銀色に輝いて見えます。
40cmを超える大型は少なく、味はやや淡泊ですがクロダイよりうまいという人も多いです。
クロダイ属魚類は変異が多く、見分けるのが難しいグループです。
ただ、琉球列島以外の日本ではクロダイとキチヌしかいないので楽ちんです。
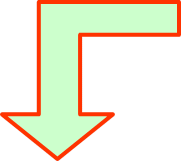
一様に灰色か暗色
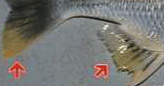

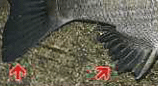
※側線上方横列鱗数は5.5枚以上
クロダイ
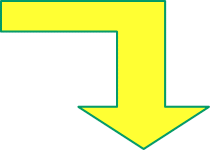
黄色か淡色
※側線上方横列鱗数は3.5枚

キチヌ
キチヌ・・・防波堤や河口などでクロダイを狙っていると、一見クロダイそっくりだがなんとなく違う・・・という魚が混じります。それがキチヌです。関西ではキビレ(黄鰭)の名前で親しまれています。キチヌについては知られていないことが多いです。
エサの食い方も荒っぽく釣りやすいので、クロダイファンにはキチヌが釣れると『なんだキビレか・・・』と小馬鹿にする人も多いです。味はキチヌの方がうまいという人が多いのですが・・・。どないやねん!
キチヌは50cmを超えると最大クラスです。