・・・主に釣りの学校で登場した魚たちを紹介します。
キュウセン(求仙)
『瀬戸内海の少年は「赤べら」に驚き「青べら」で大人になる』という言葉があるようで、たしかに子どもの頃、初めて釣りに連れて行ってもらい、その時最初に釣った魚がベラだったような・・・無知な“少年”は「わぁ!熱帯魚だ!!」とたいそう興奮した記憶がありますが、派手な模様と色のものが多いベラ科魚類、釣り少年たちが初めて直に触れる「熱帯魚」がベラ類なのかもしれませんね?
釣り人にとってベラ科の小型のものの代表は文句なしにキュウセンでしょう。他種と混称して一般的にキュウセンをベラ(関西の方言ではギザミ)と呼びます。キュウセンは夏の投げ釣りの代表魚です。雄と雌で色が著しく違います。小さいころは体色が赤っぽい雌、大きくなって性転換した雄は緑色が強くなります。だから関西では雄を青ベラ、雌を赤ベラと呼びます。
もう少し詳しく述べると、ベラ類全体でも雌型は赤っぽいものが多く、雄型は青っぽく大型が多いです。雌性先熟の機能的雌雄同体魚、簡単に言うと「性転換する魚」です。ただキュウセンやホンベラなどは、はじめから雄の固体もいて、それらは一次雄と呼ばれ外形は雌と同じです。ベラならすべて性転換すると思っている人もいますがそうではありません。整理すると、赤は雌か一次雄、青はすべて雌が性転換した二次雄です。
キュウセンは冬場に水温が下がると砂の中に潜って冬眠し、日が沈むと同じように砂に潜って眠る習性があるため、夏場の昼間しか釣れません。関東では釣れると「なんだぁ、ベラか・・・」と下魚扱いされますが、関西特に瀬戸内海では人気が高く、非常に珍重されます。ベラ専門の乗合船にはぎっしり釣り人が乗り込んでいます。関西でのみ人気が高いのは、冬は水温が下がり成長がおそい瀬戸内のベラは他の海のベラより身がしまっておいしいからではないでしょうか?釣りだけでなく、色鮮やかなうえにヌメリがあるため食べない地方も多いようですが、外見に似ず味は上品で、身はやわらかいです。雄のほうが雌よりおいしいです。ちなみに日本記録は34.7cmです。実際の釣りでは30cmを超えることはまずないです。
ベラ科の2大スターはここまで述べたキュウセンとあと一つはコブダイです。姿は似ていませんが・・・
呼び名の通り成長した雄は前頭部がコブ状に大きく突き出し、とてもユーモラスな顔つきになります。地方によってはカンダイの呼び名でおなじみです。(雄をコブダイ、雌をカンダイと呼び分けることもあります)幼魚のころは鮮やかな朱色の体にやや黄みがかった白いストライプが走り、背ビレや尻ビレに大きな黒斑が散る美しい魚ですが、成長とともにストライプも消え、体色もなぜか黒ずんで(老成すると紫紅色一色)しまいます。しかも雄だけにオデコに大きなコブができ、いっそう醜悪な顔に変身してしまいます。ベラ科の魚ですが体長は1mを超え、ものすごい馬力があり、怪力の持ち主で、一気に竿をしめこんでくるので釣り味は抜群です。ただ昔はそんな1mちかいコブダイがよく釣れたそうですが、最近はめったにお目にかかれなくなっています。瀬戸内海の投げ釣りで30cm級の若魚は投げ釣りでも時々釣れます。日本記録は116cmです。
ただ、釣られるとすぐにいなくなる種でもあるので、特に幼魚は大事にしないといけないのではないかと私は思います。




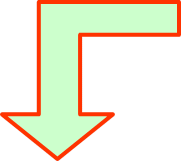
ない
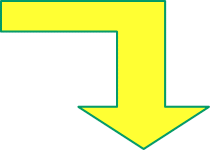
ある
キュウセン(雄)
キュウセン(雌)

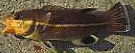
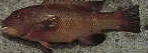
コブダイ幼魚
コブダイ若魚
コブダイ(ベラ科コブダイ属)
野球せん?・・・・・・すみません(#^.^#)
スズキ(鱸)
ほぼ日本全国に生息(日本近海固有種)し、河口・大都市の港・湾・砂浜・磯場と場所を問わずに釣れるせいでしょうか、海のルアーフィッシングでは最も人気のある魚のひとつがスズキです。河口から川の中にも平気で入り、特に大型はかなり上流まで侵入していきます。クロダイなども河口に入りますがスズキほどは川をのぼりません。河口域は塩分や温度などの環境が著しく変化し、生き物が棲むにはきびしい面もありますが、一方栄養は豊富で、それなりに色々な『いきもの』が生息しています。スズキは塩分調整機能の獲得という生理的な壁をあえて克服し、河川にも入っていき、誰にも邪魔されることなく豊富な餌をむさぼり食べてたくましく生きているのです。最近は稚魚にとって重要な生育場となる藻場の減少が魚類資源減少の一因とされていますが、これはスズキにはあてはまらないようです。スズキの資源が減少したという話を聞かない理由はスズキのこの河川侵入にあるのかもしれませんね??
シルバーメタリックのスマートな体と精悍な顔つき、ハリに掛けてからの豪快な“エラ洗い”と呼ばれるファイト(全身を空中にあらわすような豪快なジャンプを繰り返しはらはらさせられます)が釣り人を魅了してやまないのでしょうか?釣りの人気はクロダイと双璧です。
スズキは成長をするにつれて呼び名が変わる出世魚としてもよく知られています。関東ではセイゴ(~24cmの1年魚))⇒フッコ(30cm~の2年魚まで)⇒スズキ(60cm~の3年魚以上)、関西ではセイゴ⇒ハネ⇒スズキ、中部地方ではフッコやハネぐらいの大きさのものをマダカと呼ぶようです。全長1メートルに達するものもあります。また湖のブラックバスに対し、シーバスとも呼ばれます。
セイゴと呼ばれるサイズだと塩焼きが一番ですが、スズキと呼べるサイズだと、あらいの他に造りや寿司のネタにもいいです。
スズキの近縁種で普通はスズキと同様にみなされていて、水揚げされる市場でもスズキとして扱われてしまうことが多いのがヒラスズキ。
体型や外形態がそっくりですがヒラスズキのほうがやや体高が高く、尾の付け根も短いです。スズキより暖かい海が好きなのか、北の地方には見られず南紀や四国東南岸、九州などに多い魚です。南紀ではモスと呼ばれ、早くからルアーの釣り場が開拓されていました。ルアーマンの間ではスズキをマル、体高のあるヒラスズキをヒラと呼ぶことが多いようです。どう猛さはヒラスズキの方が上で、ヒットしてからのファイトはスズキを上回り、また味もスズキよりおいしいという人も多いです。あまり詳しい生態はわかっていないのですが、海が荒れるとどこからともなく磯にあらわれて、白波のたつ「さらし場」などの下に潜むようです。よって凪(なぎ)の時はあまり釣れず、少し荒れ気味で波立つような日によく釣れるそうです。じゃあ凪の日はどこに行っているのだろう・・・?料理法はスズキと同じです。
少し話が横道にそれますが、先日見た雑学の本に「○○はスズキの仲間だ」と書いてありました・・・
他の雑学本でも同様の表現を見かけたことがありますが、この『スズキ』が『スズキ科』を意味するならたいてい嘘であり、『スズキ目』なら意味がありません。
日本産の『スズキ科』魚類は12属23種と今のところされていますが、かなり混乱しています。もっと研究が進めば何種かはスズキ科ではなくなるとも言われています。『スズキ目』魚類ならば118科1756種におよび、日本産魚類のほぼ半数が「スズキ」になってしまいます。普通に「スズキ」といえばそれは「スズキ属」を意味します。日本のスズキ属は2種でこれが上で述べたスズキとヒラスズキです。
「スズキ属」であるが日本産ではなく「外来魚」なのがタイリクスズキです。ルアーマンが「斑点鱸(すずき)」とか「星鱸」と呼ぶものです。
養殖業者によって中国や韓国、台湾などから持ち込まれたものが逃げ出して1990年頃から西日本を中心に広がっていきました。発見のきっかけになったのは愛媛県の宇和島で、このタイリクスズキの養殖のメッカです。今では東京湾からも釣られているようです。ブラックバスの問題もそうですが、外来移入魚はどんな被害をもたらすか誰も想定できず、今後注意深く見守ることが大事だと言われています。
今のところスズキをはじめとする在来種や生態系に影響を与えているというような研究結果は出ていないようですが・・・
味はスズキよりおいしいという人も多いです。
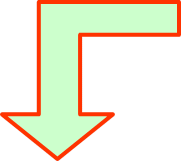
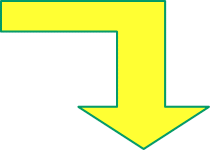
短く太い
長く細い



ヒラスズキ(スズキ科スズキ属)
短い
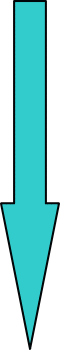
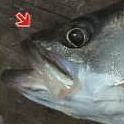

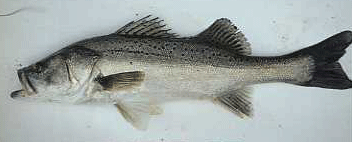
タイリクスズキ(スズキ科スズキ属)
ベラ科キュウセン属
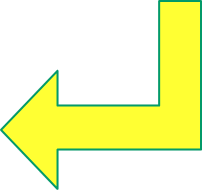
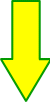
長い


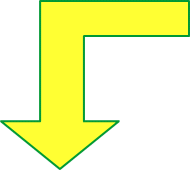

スズキ(スズキ科スズキ属)
注意・・・全長25cm以下で時に黒点があります。
ニベ(? )
昔からイシモチ釣りといわれているのは、ニベのことで、瀬戸内海ではコイチもまじります。ニベとコイチの外見からの見分けは非常に難しい(下図は典型的な一例)です。船から狙うことの多いシログチも合わせて、静岡から関西、四国にかけてはニベ科の魚を混同してイシモチまたはグチと呼ぶところが多いです。グチという名前の由来は釣り上げたらすぐにわかります。ニベ科の魚はウキブクロを使ってグウグウ音を出すものが多く、グウグウとグチをこぼすが如くなくので「グチ」になったのです。ちなみに英名でも「ドラムフィッシュ」といいます。海底10mほどのところからの声が船上に聞こえるほどの大きな声(?)で愚痴をこぼします。
主にカマボコの材料として使われていますが、鮮度のよい釣りたてのものは刺身にしてもいけます。
ニベとコイチ、本当に見分けが難しくて研究者でも混乱しておりよくわかっていません。特に瀬戸内海で釣れるものがよくわからないそうです。どうもコイチが多くてニベも混じる・・・こんな感じのようです。ニベは大きくなり70cmは優に超えるようで、一方コイチはニベほど大きくならないようです。
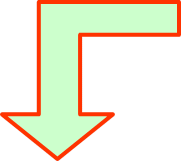
ある


シログチ(ニベ科シログチ属)
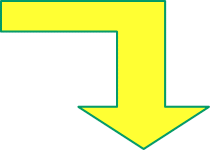
ない
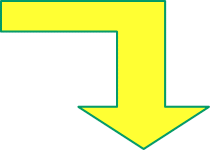
白っぽい
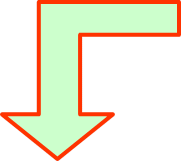
黄色っぽい
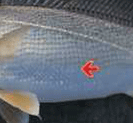
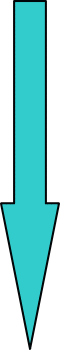
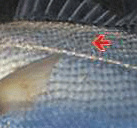

ニベ(ニベ科ニベ属)

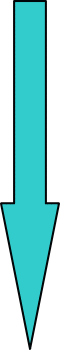


コイチ(ニベ科ニベ属)
※あくまで典型的な一例です。
DNA以外での見分け方は本当に難しいです。上で図解したのは“典型的な例”。
下の写真は「顔見たら違うでしょ?」という無責任な言い方して逃げたくなる例です(~_~)
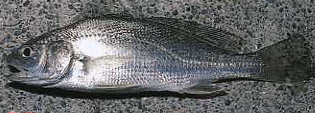
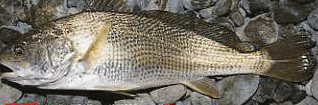



ニベ
コイチ
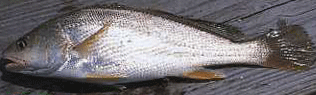

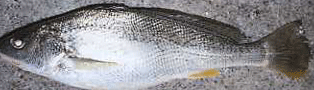


写真を見比べながら『傾向』で表現するなら・・・
腹側の体色が白っぽいとニベ、黄色いとコイチ。
上顎と下顎がほぼ同長ならニベ、上顎が長ければコイチ。
口が小さければニベ、大きくへの字ならコイチ。
ねっ!顔が違うでしょ???
カワハギ
釣りの対象魚で、全国的にポピュラーなのはカワハギとウマヅラハギです。関西ではどちらもハゲで通り、カワハギをマルハゲと呼んでウマヅラより格上に区別しています(明石ではウマヅラハギをナガハゲと呼びます)。どちらもうまいですが、より味がいいのはカワハギで秋から冬、肥大したキモ(肝臓)が最高です!!『海のフォアグラ』と言われるほどです。
関東ではカワハギ釣りの歴史が古く、独特の仕掛けを使う船釣りが盛んで、『一度はかかる“カワハギ病”』とも言われ冬場の釣りものとして定着しています。関西では専門の船はほとんどありません。関西の乗合船などではタイ釣りなどのうれしい外道です。
ウマヅラハギは沖合いで群れをなす“ハゲ”であり、カワハギは浅場の岩礁近くで単独生活をする“ハゲ”であることが多いようです。
カワハギはとても用心深くて、エサを少しずつかじるエサ取りの名人です。エサを見つけるとまるでヘリコプターのように水中でホバリングして、おちょぼ口でエサをかじり取るようにして食うため、なかなかハリに掛からないのです。それを引っかけるのがやはり『腕』ですね(>_<)
関西ではハゲちりなどの鍋物が定番ですが、実際はカワハギではなくウマヅラハギが代用品で出ていることも多いようです。
カワハギより顔が長く、馬の面(つら)に似ていることから命名されたウマヅラハギ。ウマヅラハギは美味しくないと嫌う人もいますが、こちらはもう少し評価されても良いのではないでしょうか?ちょっと磯臭いこともあるのですが、新鮮なものはきちんと処理するとカワハギと同じように美味しいです。この魚はカワハギよりいやしいのか、エサを追いかけてどこまでも浮上してきますが、エサ取りのうまさにかけてはカワハギと変わらず、ハリにかけるのが難しいです。ハリに掛かると、鋭角な引き込みと海面に上がってくるまでの間に連続的な引きをみせるのが特徴です。
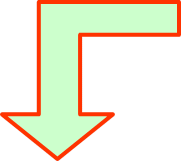
ある
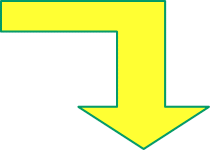
ない

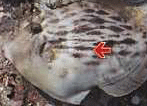
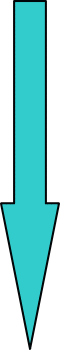
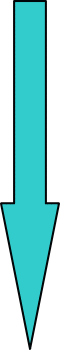
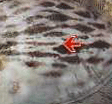
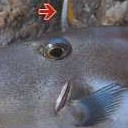

ウマヅラハギ(カワハギ科ウマヅラハギ属)

※カワハギの雄は第2背鰭の第2軟条が糸状に長くのびています。
カワハギ:雄

カワハギ(カワハギ科カワハギ属)
マゴチ
コチという場合、マゴチを指すことが多い。マゴチは沿岸の浅い砂底に棲み、ヒラメと並ぶ「生き餌(小型のキスなど)」で狙う魚食魚のスター(高級食材)です。最大で1mにもなる大型魚です。白身の魚で、薄作りの刺身は「テッサナミ」と呼ばれるほど味がよく、フグに匹敵するといわれています。冬はちり鍋にも適しています。
照りこむほどに味がよくなると言われているこの魚は、東京湾で『照りゴチ釣り』と呼んで、夏の風物詩になっていますが、関西ではマゴチ専門の乗合船などはないようです。
マゴチはエサを噛み切らずに口に入れておくだけという習性があるので、合わせるタイミングが難しいです。生きエビなら4~6秒、ハゼだと10~15秒ぐらいが食い込ませるための目安のようです。
釣りではほとんど掛かりませんが、ヨシノゴチという魚もいます。魚の生態研究者は長い間マゴチとヨシノゴチを同種と思い込んでいたようですが(別種と分けられたのは1970年前後)、西日本の漁師は昔からマゴチを「くろごち」、ヨシノゴチを「しろごち」ときちんと分けていたそうです。その名の通り、ヨシノゴチは白っぽく、マゴチは体に数本の黒褐色帯あります。「しろごち」は美味しくなく市場価値もまったく違い、知らないのは研究者だけだったとはなんとも面白いお話です・・・
あまり美味しくないのに、主に関東のテレビや新聞でネズミゴチ(天ぷらで珍重される)と間違えられられているのがメゴチ。せいぜい25cmぐらいの小型種で第一背鰭の後半が黒く、尾鰭に縦帯がなく、体の斑点が不定形です。美味しくないのでおもに練り製品の原料です。
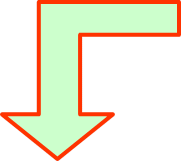
広い
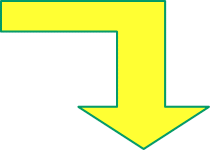
狭い
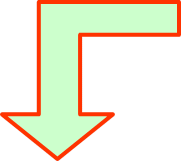
小さく不明瞭
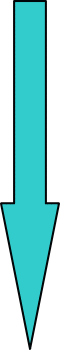
大きく
明瞭
以下写真省略
・吻が眼径と同じで短いとオニゴチ
吻が眼径より長くて・・・
↓
・腹鰭に斑点があり、体の横帯が明瞭ならワニゴチ
・腹鰭に斑点がなく、第1背鰭の黒斑が後半部にもあり、尾鰭に黒色縦帯がないならメゴチ
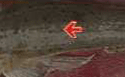




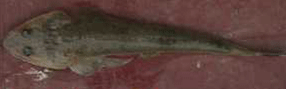
マゴチ(コチ科コチ属)
ヨシノゴチ(コチ科コチ属)

メゴチ(コチ科メゴチ属)