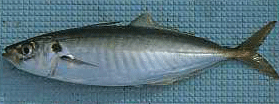
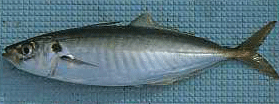


�I�j�A�W

�A�J�A�W
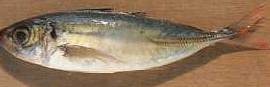
�Ԃ�

�}���A�W
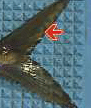
�Ԃ��Ȃ�
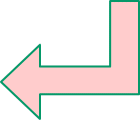
����ɁA���h���Ԃ��ƃI�A�J�����B
���h���Ԃ��Ȃ��Ȃ������h�̌㉏���Ԃ��ƃ����B
���h�����h�̌㉏���Ԃ��Ȃ��āA�c�т�����N�T�������A�c�т����F��������A�W�B
�i�ʐ^�͏ȗ��E�E�E�j
���h�́E�E�E
�������ג����E�E�E
�K�x�ɍג����E�E�E
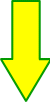

�̂́E�E�E
����ɁA�ҊW�㉏�����ނƃ��A�W�A���܂Ȃ��ƃz�\�q���A�W�B
�i�ʐ^�͏ȗ��E�E�E�j
�㔼��
������
����
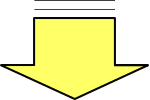
�}�A�W

�O����
�ɂ�����

���ŗi��傤���j���u���v�ƌĂ�Ă���i���낱�j�̂��ƁB
�A�W�ނ̑������C���V�ނ̕����ɂ���ό`�����B
�ŗ͑����́E�E�E
�Ȃ�
����
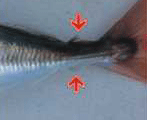
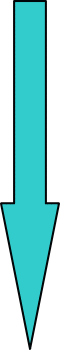

�������h�i���傤�肫�j���w�h�i�Ђ�j���\�h�ɂÂ��Ĕ��h�܂ł̊ԁi�������j�ɏ��������ꂽ�h������ꍇ�A����������h�Ƃ����B�����A�W����c���u������1����A�I�j�A�W�����T�o�ނ̂悤�ɐ�����Ă���̂������B
�������ɏ����h���E�E�E
�̂̒������������
�̂̑O������

�����������́E�E�E
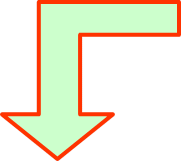
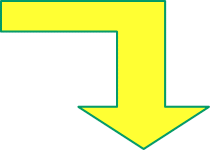
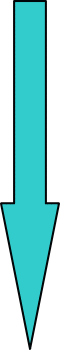
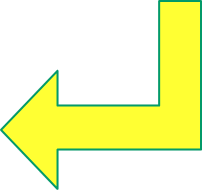
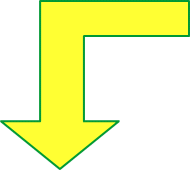
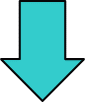
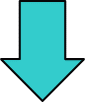
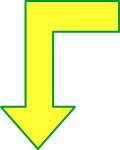
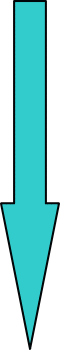
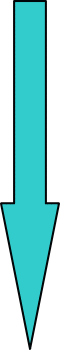
���������������ߐH��ł����Ȃ��݂̃}�A�W�i�A�W�ȃ}�A�W���j�B10�`15�����̏��A�W�͖h�g��ŃT�r�L�ނ�ł悭�ނ�邪�A�������ő_���A�W�͂ЂƉ����ӂ������傫���ł��B�A�~�G�r�Ȃǂ��T���Ȃ���A���J�[�����낵�ċ[���o���Œނ�Ƃ��낪�����ł����A���ΊC�����Ȃǒ��̑����ꏊ�ł͑D�𗬂��Ȃ���[���o�������Œނ�܂��B�}�A�W�͂������③������܂��ł����A������Ă������������ł��ˁI�I
�}�A�W�ɂ͒n���n�Q�������āA�`�Ԃɂ��ψق�����A�����҂̊Ԃł��c�_�⍬��������悤�ł��B
�}�A�W���ꑫ�x��ăV�[�Y���ɓ���̂��}���A�W�i�A�W�ȃ����A�W���j�ł��B�悭�����̂�����^�͑���≖�Ă������������ł��ˁB
���ł͏��A�W���u�Ԃ����v�Ɓu�����v�ɕ����邱�Ƃ����邻���ł��B
�Ԃ��̂͐H�ׂĂ��������A���̂͋����̂Ő����a�Ɍ����܂��B�Ԃ��}�A�W�Ő��}���A�W�ł��B�}���A�W�̓����A�W���̒��ň�ԉ��ݐ��������ł��B
�Ƃ肠�����͂����܂ŁB
�u�}�A�W�ƃ}���A�W�v�͈ꔭ�Ō���������悤�ɂȂ�܂�����?
���{�̐H��Ń|�s�����[�ȃA�W�͏�ŏЉ���}�A�W�Ƀ}���A�W�����A�u���⍂�����i�_�l�ŗL���ȃV�}�A�W�A�J���p�`�A�q���}�T��������Ƃ����A�W�Ȃ̒��Ԃł��B�u���͐����ƂƂ��Ɂi�傫���Ȃ�ɂ�āj���O���ς��o�����ł�����ł̓c�o�X�˃n�}�`�˃��W���˃u���A�֓��Ń��J�V�˃C�i�_�˃����T�˃u���ƂȂ�܂��B�{�B�̑�\�I�Ȃ����ƂȂ�A�{�B�̐���Ȋ��̃n�}�`�Ƃ����Ăі����S���ŗ{�B���̂̑㖼���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�u���ƌĂׂ�̂͒n���ɂ���ĈقȂ�悤�ł����A��ʓI�ɂ͍Œ�ł�80�Z���`�ȏ�̂悤�ł��B
�ł͎��ɁA������������ƌ����Ă���w�q���}�T�ƃu���̌��������x�ɂ��āE�E�E
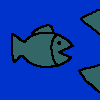
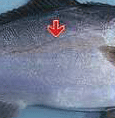
�u���i�A�W�ȃu�����j
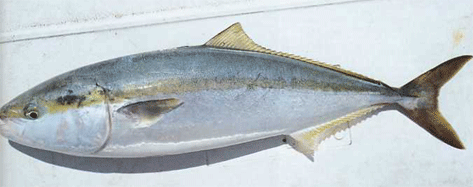
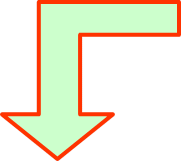

�p��
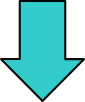
�q���}�T�i�A�W�ȃu�����j

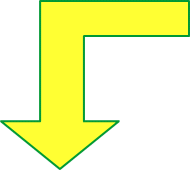
���h�����h���Z��
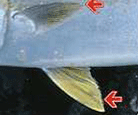
���h�ƕ��h���قړ���
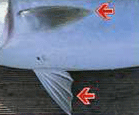
�i�R�[�i�[���j�ۂ�

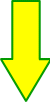
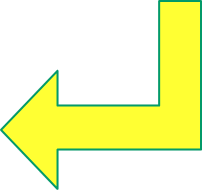
�゠����[�́E�E�E


�����w�h�E�\�h��[�͂��Ȃ荂��
�J���p�`



�q���i�K�J���p�`

����
�Ȃ�
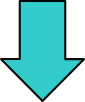
����
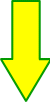
���h���t��[�́E�E�E
�Ȃ�
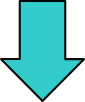
����
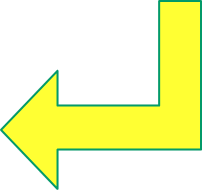
���ʂ�Αт��E�E�E
�c���u��

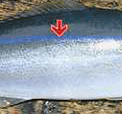
�Ȃ�
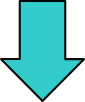
����
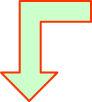
�̂ɐ��c�����E�E�E
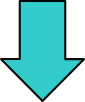

�V�}�A�W�i�A�W�ȃV�}�A�W���j

���݂̊C�̊�ʑтȂǂɑ����B
�C���̈����X�^�C�������Ă���̂ŊO���ł̓f�r���t�B�b�V���i�����̋��j�ƌĂ�ŐH�ׂȂ����Ƃ������悤�ł��B
�g�Ղ�_�R�h�ƌĂ��悤�Ɋ��ł͉Ăɒ��d���܂����A�֓��ł͓~��̂��̂��D��ŐH�ׂ�悤�ł��B
�C�C�_�R

���^�Ŋ����Ȃ�Ɠ��ɔсi�������߂����j�̂悤�ȗ����т�����l�܂�Ƃ��납��C�C�_�R�ƌĂ�܂��B���˓��ł͔т̓���Ȃ��Y���X�{�P�ƌĂԂ����ł��B���˓��Ⓦ���p�Ȃǔg�̐Â��Ȑ��[10�`20�b�ȍ���̓��p�ɑ����ł��B�C�C�_�R�e�����ƌĂԓƓ��̓�����g���Ēނ�܂����A�֓��ł̓}�_�R�ނ�̃e���������^�ɂ������̂Ƀ��b�L���E��u�^�̎��g�Ȃǂ���Ēނ�A������ł̓G�T�͕t�����ɔ���p�[���F�̂����e�������C��Ŗ�点�Ċ|���܂��B
�v���|�[�V�����̓}�_�R�Ɏ��Ă��܂����A�C�C�_�R�͖ڂ̋߂���2�̋��F�̖�̂���̂������ł��B
�܂��畆�͂ԂԂŁA�Ƃ���Ƃ���̍����c���܂�����܂��B
�D�𗬂��Ȃ����������悤�ɗU���A�W�������Əd�݂����������C�C�_�R��������؋��B�升�킹�����Ď�������܂Ȃ��悤�Ɏ�荞�݂܂��B�����͎�Ɏς��B�����������C�C�_�R���{�E���ɂ���āA�����X���ӂ��Ď�ł悭���ށB�n�܂�����Ă����Ƃ�ŏグ��B�^�R�͎ς�����ƌ����Ȃ�̂ŁA���ł�̎�ɂ͑��̍ޗ����قڎς����Ƃ���ʼn����A���߂���x�Ɏς܂��B
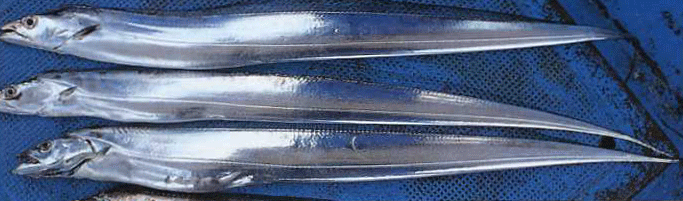 ������ɂ��ė����j�������܂��B�a���̗R���͂������炫�Ă���Ƃ������邪�A�����Ɏ��Ă��邩��Ƃ����b������܂��B���Ă��ĉ����{���Ȃ̂��E�E�E�H�����A��������̔��B����ȑO�̍]�ˎ���A���łɂ��̋����^�`�E�I�ƌĂ�Ă������Ƃ���A�������̂ق����L�͂ł͂Ȃ��ł��傤���H
������ɂ��ė����j�������܂��B�a���̗R���͂������炫�Ă���Ƃ������邪�A�����Ɏ��Ă��邩��Ƃ����b������܂��B���Ă��ĉ����{���Ȃ̂��E�E�E�H�����A��������̔��B����ȑO�̍]�ˎ���A���łɂ��̋����^�`�E�I�ƌĂ�Ă������Ƃ���A�������̂ق����L�͂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�q�����i�q�����ȃq�������j