海&釣りの用語集
上げ潮・・・干潮いっぱいから潮が満ちてくる状態。一般的には下げ潮のときよりも上げ潮の方が釣果はいいとされています。
アジロ・・・好漁場(方言)
アタリ・・・釣り人が魚の反応を知覚する瞬間!自分の竿のアタリより、他人の竿のアタリの方ばかりが気になることも多い。これが全くないと釣り人にとっては非常に辛い。
アブレ・・・魚が全く釣れないこと。ボウズと同義語。
合わせ・・・アタリがあった時に竿を動かして魚をハリに掛けること。アタリがあった瞬間に合わせる早合わせや、ゆっくり確かめるように合わせる聞き合わせなどがあり、狙う魚の種類や状況によっても合わせ方が異なる。
合わせ切れ・・・魚がハリに掛かって合わせた瞬間、糸の強度より強い力が加わり、そのショックで糸が切れること。精神的ショックも大。
生き締め・・・魚の鮮度(旨み)を保つために生きているうちに殺すこと。釣りでは殺すことを「締める」という。自然に死ぬのを待つと、魚に強いストレスを与え不味くなる。エラや血管を切って血を抜く血抜き(臭みをとる)とは意味合いが違うが、大型魚や青物ではたいてい組合わせて行われる。
居食い(いぐい)・・・魚がその場を動かずにエサを食ってしまうこと。竿先にアタリが出ないので見逃しやすい。
イケス・・・釣った魚を船内で生かして保存しておく場所。空であることの船が多い・・・
一文字・・・「いちもんじ」と読みます。防波堤の関西風の言い方。
一束(いっそく)・・・魚100尾を1束として数える単位。
糸フケ・・・道糸のたるみのこと。風や波、潮流によって起きる場合がある。たるんだ糸を張り直すことを『(糸)フケをとる』という。大物が掛かって糸がフケることもあるので、糸フケを取るときは要注意。
糸ヨレ・・・ミチ糸やハリスがねじれること。スプリングリールでは特に発生しやすい。魚がハリ掛かりしリールを巻くときに発生する。糸の強度が低下する原因となったり、エサが回転する(⇒食いが落ちる)ため少なくする必要がある。そのため、仕掛けには糸ヨレを防ぐためサルカンやスナップ付きサルカンなどが上(下)に付けられている。
入れ食い・・・仕掛けを投入するたびに魚が釣れること。釣り人にとってはたまらない一瞬であり、自然保護の大切さなど消し飛んでしまう・・・
浮かす・・・掛けた魚を水面に浮かせること。魚を空気を吸うとおとなしくなるので取り込みやすくなる。タモ入れのコツ。
うき・・・船釣りではあまり必要としないもの。釣具屋が釣り人を釣るための小道具!?
うき止め糸・・・うきとの摩擦で糸が痛まないような専用の糸。
うねり・・・大きく起状する波。うねりが出ると船が揺れやすい。
上潮(うわじお)・・・海面に近い表層の流れのこと。上潮が流れていても、下潮が流れていないときはたいてい魚の食いが悪い。
上物(うわもの)・・・一般には海面付近を泳ぐ魚(カツオやヒラマサなど)を指す。釣りにおいては中層まで浮いてくるクロダイやメジナなどの魚全体をいう。海底付近にいる魚は底物という。
餌木(えぎ)・・・イカを釣るための、エビや魚の形をした擬似バリ。これを使った釣りのことをエギングという。
エサ①・・・これがないと釣れない。様々な種類があるが、エサの購入総額と釣果は必ずしも合致しないもの・・・
エサ②・・・海の食糧難を解決する救世主。
エサトリ・・・メインの魚がエサに食いつく前に高価なエサを横取りし、釣り人を馬鹿にする魚たち。「エサ盗り」と書くべきか?小魚のエサトリをジャミ、エサ取りとコツコツしたアタリをジャミアタリということもある。
枝ハリス・・・仕掛けの途中から枝のように出ているハリス(ミチイトとハリの間につけるイト)のこと。エダスともいう。木の枝のように見えるからこの名が付けられた。木の幹の部分に当たる糸はミキ糸、またはモトスという。
鰓洗い(えらあらい)・・・スズキが口の中の異物(ハリなど)を吐き出そうと頭を振りながら海面をジャンプする様子をいう。エラがするどいのでハリスが切られてしまうことがある。対処法としては糸の張りを保つことが大事。
追い食い・・・1尾がハリに掛かったあと、残りのハリに他の魚が食いつくこと。魚1匹が掛かると、その魚が暴れることにより、他のハリが踊り、いい誘いになる。小アジを釣るサビキ釣りでは必須のテクニック。
陸釣り(おかづり)・・・陸地から釣ること。おかっぱりとも言う。
置き竿・・・サオを置いてアタリを待っている状態。手にサオを持ってアタリを待つことを持ちザオという。
送り込み・・・アタリがあった時にすぐに合わせず、しっかりエサを食わせるためにサオ先を下げたり、リールから糸を送り出してやる動作のこと。
落ち・・・浅場にいた魚が、越冬や産卵のため深場に移動すること。
おでこ・・・ボウズと同意語。最近はあまり使われない。
落ち込み・・・急に深くなっている場所のこと。ボウズの時の気分ではない。
オマツリ・・・技量の差や風向きなどで仕掛け同士がからみ合うこと。けっしてめでたくはない・・・
面かじ・・・だ輪を右にまわせ!
オモリ・・・重さは号数で表示され、、釣りの種類や地形、潮の流れによって様々な形や重さを使い分ける。夜行釣リの夜光オモリやカレイ釣りによく使われる蛍光色の物もある。
オモリ負荷・・・そのサオが効果を発揮するために一番適したオモリの指標。
泳がせ釣り・・・小アジなど生きた小魚をハリに掛けて泳がせながら大型魚を狙う釣り。ノマセ釣りともいう。
ガイド・・・釣りを教えてくれる人のことではなく、サオにセットされたミチ糸を通すリング。
掛かりますか?・・・釣れていない人に対する思いやりのある問いかけの言葉。「釣れますか?」は腕のある人にかける言葉・・・
カケ上がり・・・水底の深場から浅場に向かう急な斜面。流れが変化してエサが集まりやすいので好ポイントとして注目される。
型・・・魚の大きさのこと。標準以上の魚体を良型と呼ぶ。
活性が低い(悪い)・・・ボウズの責任を魚に転嫁できる便利な言葉。決して腕が悪いわけではない・・・
空合わせ・・・アタリがないときでも一応合わせてみること。結果的に仕掛けが動き、誘いとなって掛かることもある。カレイ釣りではかなり有効!
ガン玉・・・色々な大きさの丸いナマリの玉。ハリスに挟んで使います。
聞く・・・魚がエサをくわえているかどうか、軽くミチイトを張って確かめてみること。そのまま合わせの態勢に入ることを「聞き合わせ」という。
キャスト・・・仕掛けを投げること。
キャッチアンドリリース・・・あくまで自然保護を目的に、釣り上げた小さい魚などを放流すること。
漁礁・・・複雑で変化に富み、魚が集まりやすくなった海底の地形。
魚拓・・・その魚、反面が既に黒くなっていませんか?「他人の魚」の使用は厳禁(ーー;)釣具屋の宣伝にも使われる。
食い・・・魚がエサを食べること。多く釣れるときなどは「今日は食いがいい」と表現する。
食い渋り・・・魚がエサを食わず、なかなかアタリが出ないこと。水温が急低下したようなときによく見まわれる現象。
口切れ・・・魚の口に刺さったハリの穴が、やり取りをしている間に大きく広がったりさけたりしてハリが外れてしまうこと。アジなどの薄い唇の魚で多いトラブル。
クーラーボックス①・・・冷えた飲料水や弁当を持っていくために使われる。ごく稀に釣れた魚を入れることにも使われる。
クーラーボックス②・・・釣行の帰りに、軽かったり重かったりするとても不思議な箱。掃除出来る日はなぜか嬉しい・・・
クーラーボックス③・・・売り場には様々なサイズのものが売っているが、釣り人に何故か大きいものを買わせてしまう魔法の箱。
クーラーボックス④・・・釣れなくても帰り道に魚で一杯に出来る魔法の箱。
グレ・・・クロダイと並ぶ上物釣りの人気魚。関西ではグレ、九州ではクロ、関東ではメジナ(正式な和名)である。以前見た釣り番組(全国大会)で、「あの見えている魚はグレちゃうか?」「おおっ!クロばい!!」「確かにメジナだね」という面白い会話が成立していました・・・
蛍光道糸・・・蛍光色(黄色やオレンジなど)を使われている道糸。糸が見やすく釣りやすいため一気に普及した。塗料そのものに若干浮力がある。
月曜日・・・昨日釣った魚のサイズがドンドン大きくなる不思議な曜日。
外道・・・本命以外の魚。種類によってはうれしい外道の時もある。プロレスラーではない。
ケミホタル・・・化学薬品による発光材。竿先やウキにつけアタリを視認するのに使う場合と、仕掛けの近くにつけ集魚目的に使われる場合がある。一般的には生物発光に近い蛍光グリーンがよく使われるが、対象魚に応じて様々な色のものが売られている。湿気や高温に弱いため、冷凍保存あるいは密閉容器や除湿剤による保存が望ましい。
50cm・・・天気予報を見て、船を出すかどうかを決断する波の高さ。
小突き・・・オモリで海底を小刻みにたたく釣法。代表的なものとしてカレイの船釣り、アナゴ釣りに用いられる。
木葉(こっぱ)・・・木の葉ぐらいの小さな幼魚のこと。
五目釣り・・・狙う魚を一つに絞らずに、いろいろな魚種を楽しむこと。五目並べをしながら釣りをすることではない。
コマセ・・・魚を寄せるためにまくエサのこと。マキエ。一番喜んでいるのはエサトリ達。
竿・・・魚を釣るための道具。竿の値段と釣り人のレベルのバランスが大事である。一度も曲がったことのない高級竿はその典型。
竿頭(さおがしら)・・・船の中で本命の魚をいちばん多く釣り上げた人のこと。帰港後のヒーロー!
先糸・・・からみを防ぐためや仕掛けを投入したときのショックで糸が切れないようにミチイトの先に付けるイトのこと。ナイロンやフロロカーボンが適している。
先調子・・・サオの先端部が大きく曲がるように作られたサオ。食い込みがよくなるとも言われている。
誘い・・・刺しエサを動かして魚の食い気を誘うテクニック。
刺し餌・・・ハリに刺すエサのこと。付けエサ、サシエ、ツケエとも言う。
サビキ・・・ハリに魚の皮やビニール片などが付いている擬似バリのこと。この擬似バリを数本用いた仕掛けをサビキ仕掛けという。
さびく・・・仕掛けを少しずつ引いて追い食いを誘うテクニック。
サミング・・・リールのスプールを指で押さえてスプールの回転を制御するテクニック。
サラシ・・・波が岩などの障害物にあたりまっ白になること。海中に酸素が供給され、また白い波が自然のブラインドになるため魚の活性が高くなる。
サルカン・・・道糸とハリスを(ヨレないように)連結するための部品。スイペル、ヨリモドシともいう。
潮・・・釣れない時の理由でよく出てくる言葉⇒「今日は潮が悪いから仕方がない」。釣れた時は潮ではなく『腕』のせいとなる・・・
潮回り・・・満月から新月までの間に、潮は大潮⇒中潮⇒小潮⇒長潮⇒若潮と変化する。陸上では一切必要ない変化。
潮だるみ・・・干潮や満潮の頂点の時に潮が動かなくなること。魚は釣りづらい。『潮止まり』ともいう。
潮目(しおめ)・・・潮の速度差によって出来る潮の境目。プランクトンなどが集まりやすく、小魚を狙う大型魚も回遊するポイント。
地合(じあい)・・・さまざまな条件が重なって魚の食いが立つ時間帯のこと。
仕立て船・・・釣り船を借り切って釣りをする船。
七三調子・・・竿の先端10分の3ほどに曲がりの支点がある竿。一番標準的な調子といわれている。
尻手(しって)・・・大物にサオを持っていかれないようにサオ尻に付けるロープ。スケベな手のことではない。
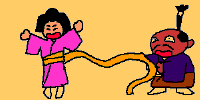
しゃくる・・・サオを上下、左右に動かすこと。“あおる”ともいう。
ジャーク・・・魚を誘うためのルアーの基本アクション。沈むタイプのルアーをキャスト後、目的のタナまで下ろし、そこからロッドを激しくあおってアクションを付けること。
sicガイド・・・シリコンカーバイドの略でガイドの一つ。熱伝導性が高いため、ラインとガイドの間に生じる摩擦熱によるライン表面へのダメージが少ない。高級ロッドのガイドとして使用されることが多い。
スターン・・・船尾を意味する。
捨て竿・・・「釣れればラッキー」という感じでとりあえず出しておく竿のこと。
スプール・・・リールの糸巻きの部分
スレ・・・口以外の場所にハリが掛かって魚が釣れること!魚が群れてエサの近くにいるとき、背ビレなどに掛かることがよくある。普通のハリ掛かり以上に暴れたり、走るため大物かと勘違いをし、上げてみてガッカリということもよくある。
すれる・・・釣り船が絶えず集まっているため魚が警戒してなかなかハリに掛からない状態。
瀬(せ)・・・沖磯のこと。地方によってハエや根ともいう。また水深が浅くなったところという意味もある。流れが早い。
船頭・・・乗合船上の王様。皆、口が悪い。魚探ばかり見てまわりを見ないプレジャーボートからは危険な存在・・・
集合時間・・・船乗りには「出航時間」を意味する。早めに集合場所に行きましょう!
スタボード・・・船の右舷を意味する。
底荒れ・・・時化の影響で海底にゴミが漂っていたり、海底の砂が舞った状態。
底を切る・・・投入した仕掛けが着底した後、底から離すこと。
底を取る・・・オモリが着底したのち、糸フケを取ったりしてから水深を正確に把握すること。タチ(水深)を取るともいう。
高切れ・・・根掛かりやキャスティング時にハリスではなく上の道糸が切れること。
タコベイト・・・タコのような形をしたビニール製の疑似餌。エサやルアーと併用するなど用途は広い。
だし風・・・岸から沖に向かって吹く風のこと。一般的にこのような風が吹いているときは釣果は薄い。
タックル・・・道具、仕掛けなどの総称。竿と同様で、持ち主との総合的なタックルバランスが必要である。
タモ・・・海に落ちた帽子などを拾うために船に置いてある備品。ごく稀に魚を取り込むときにも使われる。
タナ・・・魚がいる場所や掛かった場所(海底から○mなど)を表す言葉。他人から聞いたタナはあまりあてにならない・・・。ちなみにタチとは水深のこと。
地球・・・ハリを掛けることができる最大のものであるが、釣り上げることは出来ない。
チチワ・・・糸と穂先あるいは金具を結ぶため、糸の先に作る輪。
チモト・・・釣りバリに糸を結びつける部分。
釣果情報・・・新聞、雑誌やインターネットで公表されているあてにならない情報源。乗合船の宣伝広告か?
調子・・・サオの硬軟を指す言葉で、サオ先の方が軟らかいものを先調子、中間部が軟らかいものを胴調子という。
釣趣・・・釣りのおもむき、味わい。素人には縁のない言葉・・・
釣具屋の店員・・・釣りの道具には詳しい方々。釣りの対象はあくまで人間。
ツヌケ・・・10尾以上釣れること。一つ、二つ、三つ、・・・九つ。十から「つ」がなくなるのでツヌケ。
釣り糸・・・魚と釣り人とを結ぶ「運命の糸」。頻繁に『バラした』責任を人間から押し付けられる・・・。ナイロン、フロロカーボン、超高強度ポリエチレン(PEライン・・・伸縮性、吸水性がほとんどなく強度が高い)に分けられる。
チョン掛け・・・エサを頭からハリに通さないで、エサの一部に引っかけるようにするエサの付け方。生きエサを弱らせない刺し方。
手返し・・・エサをつけて仕掛けを投入し、巻き上げる一連の動作のこと。数を釣るためには必須の技術。
手釣り・・・船釣りなどで、サオを使用せずミチ糸を直接手で持ち釣る方法。手軽ではあるが、対象魚の習性や誘い方などを熟知しておく必要がある。
デキ・・・その年に生まれた当歳魚のこと。
テンビン・・・仕掛けと道糸の間に付けるL字状の金具。腕と呼ばれる部分とオモリを固定する部分からなっている。糸の絡みを防ぎ、魚の食い込みがよく、アタリが伝わりやすい。片テンビン、両テンビンや仕掛けが自由に動く遊動式テンビンなどがある。カレイ釣りでは最も一般的な仕掛け。
胴調子・・・サオにある一定の負荷をかけサオを曲げたとき、中心部付近からサオ先にかけてが曲がる調子のこと。この調子のサオは、魚を掛けてからが面白く、サオ全体の弾力で魚の強い引きを吸収し、ばらしにくく、細いハリスの使用可能である。
胴突き仕掛け・・・一番下にオモリをつけ、ミキ糸に数本の枝バリを付けた海釣りでは一般的な仕掛け。
とも・・・船体後方の釣り座や船の船尾をさす。
ドラグ・・・設定した以上の力で引っぱられたときに、リールのスプールが逆転してミチイトを送り出す機構のこと。
取りかじ・・・だ輪を左にまわせ!
鳥山・・・大型魚に追われて海面に集まった小魚の群れを追い、海鳥たちが群れている状態。漫画の作家ではない。
流し釣り・・・アンカー(錨)を入れないで船を流しながら釣ること。
凪(なぎ)・・・風も波もない海の状態。ベタ凪ともいう。
投げ釣り・・・釣れないと、ただ投げるだけで『なげやり』になる。バッティングセンターで素振りをするのと同じ・・・
ナブラ・・・大型回遊魚に追われた小魚の群れが海面近くに集まっていること。
逃がした魚・・・姿を見ていないにもかかわらず、実際の寸法より必ず大きい魚。また日を経つにつれどんどん大きくなる傾向もある。
2枚潮・・・上下の流れの方向が違う状態。このような時は重めのオモリを使用する。
縫い刺し・・・一般にイワムシなどのエサをハリに付けるとき、ハリで縫うようにしてエサをつける方法。ハリの形に沿って付ける場合は通し刺しという。これら2種類の付け方は投げ釣りのエサ付けの基本。
抜き上げ・・・玉網などを使わずに海面から魚を引き抜くように釣り上げること。
根・・・底の岩礁など起伏のあるところ。沈船や人工漁礁など人工的に作ったものもある。
根掛かり・・・大物を釣ったと勘違いを起こさせる不思議な現象。竿は大きく曲がります!!
根魚(ねざかな)・・・水底や海藻の茂みに住み、移動しない魚。アイナメやカサゴなど・・・
根ズレ・・・仕掛けが海底の障害物にすれること。根ズレはバラシの第一要因。
年なし(ねんなし)・・・歳がわからないという意味が込められた老成魚。当然大型。
納竿(のうかん)・・・サオを片付け釣りを終了すること。シーズン終了を意味する場合もある。
のされる・・・魚の力が強く、サオを倒されてサオと道糸がまっすぐになること。
乗っ込み(のっこみ)・・・魚が産卵のため沿岸の浅場に接近してくること。
のる・・・魚がハリ掛かりしたこと。
場荒れ・・・一つのポイントで、多くの釣り人がサオを出し、その釣り場であまり魚が釣れなくなってしまうこと。
バウ・・・船首を意味する。
爆釣(ばくちょう)・・・まさに奇跡。滅多にない(>_<)
波止(はと)・・・防波堤の関西風の言い方。
早合わせ・・・かすかなアタリが出た瞬間に合わせをすること。
バラした・・・口にしたくない言葉。ハリに一度掛かったが、最終的に取り込めなかった状態をさす。バラした魚も実寸法より大きくなる傾向がある。
ハネ・・・釣魚図鑑でも登場したがスズキの幼魚。大体40cmぐらいを指し、スズキと呼べるのは60cm以上である。しかし釣りの世界でもインフレが進みどんどんスズキが釣れている。
ハリ①・・・魚を釣るために最低限必要なもの。狙いに合わせて色々な専用バリが売られている。
ハリ②・・・ 魚を釣るより先に自分を釣ることになる道具。 釣られる魚の辛さを体感できる。
ハリス①・・・ハリに結ぶ糸のこと。
ハリス②・・・いろいろと結べるようになったら「ど素人」の「ど」が取れる。自作の仕掛けで釣れるようになったら「素人」脱出!?
バース・・・船を係留する場所。一部の居酒屋では現在の外国人助っ人との対比によく使われる。
バッククラッシュ・・・両軸受けリールでスプールが回りすぎ余分な糸が出て絡むこと。仕掛けを飛ばすときになりやすい。最近では防止機構が取り込まれているが、使いこなしには慣れが必要。スピニングリールでは機構上、バッククラッシュが発生しないので初心者向け。
ヒット・・・魚がハリに掛かること。
ヒロ・・・長さを表す表現である。ハリスの長さや、タナを表現するのに用いられる。両手を広げた時の長さを指し、人によって長さの異なる不便な表現。話し手の身長を考慮して補正が必要な単位。一般的には1m50cm相当(昔の表現だと5尺(1.515m)または6尺(1.818m))を表します。
不条理・・・ボウズで帰港する時、防波堤で釣り人が魚を釣り上げている姿を見たときの気持ちを表す。
プレジャーボート・・・釣りやそのほかレクリエーションのために使われるヨット、モーターボート及びその他の船舶の総称。国土交通省の調査によると、全国の水際線近傍で確認されたプレジャーボート数は36.6万隻(平成14年調査)で、そのうち約2/3(登録制度が出来たため少し減少しました)が不法放置艇であるという結果を把握しているようです。車と一緒で、乗るならきちんと泊めろー!
房掛け・・・イワムシなどを1つのハリに付けるとき、1匹ではなく2~3匹を房状にしてエサの硬い先端部分をちょこんと掛けるエサの付け方。魚に対するアピール度が増し、食いの悪い時などは効果的。
ぶっこみ釣り・・・広い意味では(比較的重い)オモリを海に投げる動作から、投げ釣り全般のことをいう。
振り出し竿・・・竿先から順番に太い部分に収納できる竿。携帯性に優れる。
へさき・・・船首のこと。
ベタ凪(べたなぎ)・・・ふつうの凪よりもさらに海上が穏やかな状態。操船には最適であるが、釣り状況としてはあまりよくない。
ポイント・・・魚がよく釣れる場所を表す。よく『ポイントは?』と聞かれるが、海上の一点を口で説明するのは困難である。また嘘を教えられたり、教える事も多いので、相手をよく知らない時は要注意。
ボウズ・・・釣り人が嫌う言葉。まさに暇な釣り&燃料代の無駄・・・。釣果を他人に問われると『まあまあでした』と具体性に欠く回答を伴い、魚を決して拝見できない(見せられない)。
呆然・・・もう少しで船に取り込める場所にいた魚が、再び大海原に旅立った時の釣り人の状態。
穂先・・・竿の先端。竿先。
ポート・・・船の左舷を意味する。
ポンピング・・・サオを大きくあおっては、道糸を巻き取る(竿を立てるときは巻かず、下げる時に巻く)テクニック。特に大型魚とやりとりする時に必要になる。
孫バリ・・・2本針仕掛けで補助的な役目をするハリのこと。親バリに対して孫バリという。柔らかなエサや大きなエサを刺すときや、生きた小魚を刺すときなどに使われる。普通は孫バリの方が小さい。
マキエ・・・本来は目的の魚を寄せるために用いるもの。しかし一番喜んでいるのはエサトリ達です。
マヅメ・・・朝、夕の薄明かりの時間帯をさす。日の出前後を朝マズメ、日の入り前後をタマヅメという。潮が澄んでいる時でも海中の透明度が低くなるため、釣りにおいては所謂『食いが入る』時間帯である。
幹糸(みきいと)・・・胴突き仕掛けなどで枝ハリスを取り付ける幹になるイトのこと。
水潮・・・大雨などで真水が大量に海に流れ込み、塩分濃度が下がった潮。釣りは期待薄・・・
道糸(みちいと)・・・リールを使用する場合はそれに巻く糸のことをいう。それ以外の釣りの場合は、竿先からハリスまでの糸のこと。
脈釣り・・・ウキを使わずに、ミチイトの動きやサオ先、手に伝わるアタリで魚がハリの付いたエサをくわえたことを感じ魚を釣ること。ダイレクトな魚信が楽しめ、アタリが手に伝わることから、合わせが遅れることが少なく初心者でも比較的簡単に魚を釣ることができる。
向こう合わせ・・・魚が勝手に走ってハリに掛かること。
藻・・・藻は水温の下がる冬場から茂みはじめ、春を越えて潮の温む頃からちぎれて消えていく。藻場は仕掛けが絡んで釣りにくいが、産卵場となるため魚が寄りつくポイント。
矢引き(やびき)・・・弓を引く状態にしたときの右手から左手までの長さのこと。当然人によって差が出る単位であるが、平均80~90cm。半ピロ(単純に1ヒロの半分)とは違うので注意(?)
酔い止め・・・睡眠薬のこと。 これを飲むと酔いからは解放されるが、暑くても寒くても、頭打っても釣りに来ていることなど忘れてぐっすり船内で眠れてしまう。 <注意>睡眠不足をさけて服用すること。
ヨリ戻し・・・釣り糸のヨレを解消してくれる便利な道具。夫婦間においてはしばしば子供がその役を演じることがあります。
ようそろ・・・現在の針路を保持せよ!
横波・・・船が最も嫌うのもの。
やんなっちゃう・・・ボウズで帰港したら他船が大漁であった時の気持ちを表す言葉。
リール・・・糸を巻いておく道具。巻き取る力が強い「両軸」、操作が簡単な「スピニング」、主に船釣りや深場で使われる両軸方式の「電動」が代表的なリール。対象魚やサオの組み合わせで使い分けます。
リールのギア比・・・ハンドル一回転で糸を巻く「両軸」のスプール、「スピニング」のローターが何回転するかを示す。ギア比5・5なら、ハンドル一回転で5・5回転する。ギア比は大きいほど速く巻き取り、小さいほど巻き取る力が強い。
リトリーブ・・・ルアーを引いてくること。
両軸受けリール・・・糸の出る向きと巻き取るスプールの取り付け方が同じ向きのリール。糸ヨレが少なく巻き取り力が強い。ドラグの効きがスムーズという利点があるが、バッククラッシュを起こしやすく、遠投力に欠けるなどの欠点がある。
両手・・・釣り中の人と話をする時に縛らなくてはいけないもの。
ルアー・・・様々な形態のものが発売されています。人によって色々なこだわりがありますが、一番最初に釣られているのは釣り人本人です。
ルンルン♪・・・釣行前日のハイな釣り人の気持ちを表す言葉。残念ながらこの状態は長く続かない。翌日は所謂「落ち込んだ日」に移行するケースが多い。
ワクワク♪・・・これもまた、釣行前日のみの気持ちを表す。
ワーム・・・ミミズ、またはミミズに似せて作った擬似餌のこと。
割りビシ・・・糸に止めやすいように割れ目を入れたオモリ。
ワンド・・・入江や小さな湾上になっているところ。